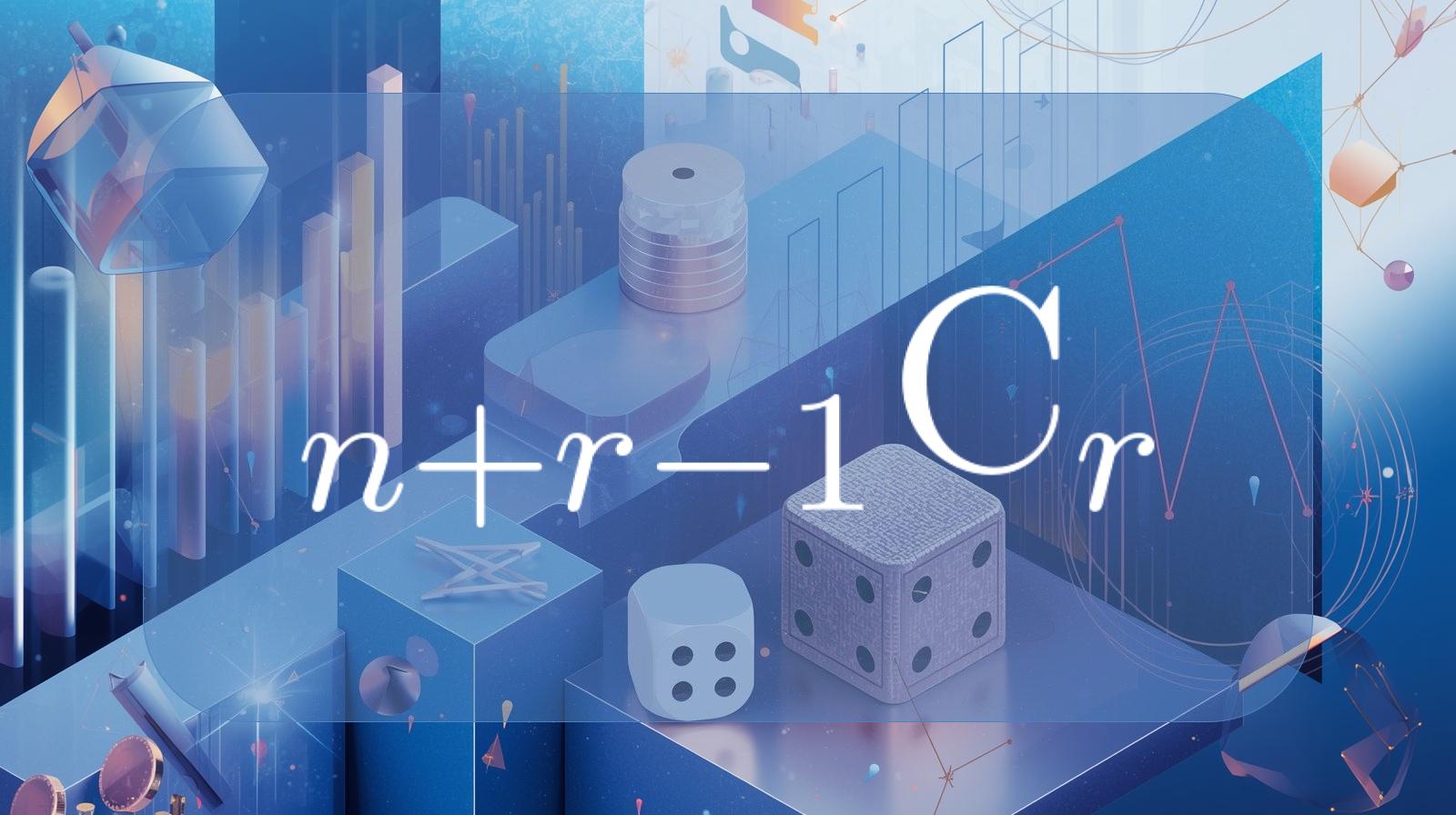§1.はじめに
異なるものの順列や組合せ,重複順列に比べると,重複組合せは難しいと考える人もいるのではないでしょうか。
異なる \(n\) 個のものから重複を許して \(r\) 個取る組合せの総数は,次の式で表されます。 \[{}_{n+r-1} \mathrm{C}_r\] 教科書などでは,この公式を得る過程で 2 つの記号○と|を使った考え方が紹介されることが多いでしょうが,説明が簡潔であるため,一読しただけではよくわかりませんでした。
そこで,もう少し掘り下げて,○と|を使った信号で相手に情報を伝えると考えると納得できたので,その考え方を残しておきます。
§2.各組合せと「○と|の配列」の対応
次の例題を通して考えてみましょう。
例題
3 種類の商品 A,B,C から重複を許して 6 個選んで買うとき,商品の組合せは何通りあるか。
組合せを考えているのですから,順序は問題ではありません。例えば,「AABCCC」も「BCACCA」も同じ「A が 2 個,B が 1 個,C が 3 個」という組合せです。重要なのは,A,B,C がそれぞれ何個ずつであるかという情報です。この情報を 2 つの記号○と|の配列で伝える信号を作ります。
A,B,C の順に個数を伝えることにしましょう。
「A が 2 個,B が 1 個,C が 3 個」であることは,次のように表すことができます。
まず「A が 2 個」であることを伝えるため,
○○
と記号○を 2 個続けて並べます。次に「B が 1 個」であることを表すために○を並べたいところですが,
○○○
としてしまうと,A と B の個数の区別がつきません。そこで,A の個数を伝え終わったことをはっきりさせるため,2 個目の○の直後に記号|を入れて
○○|○
とします。さらに,B と C の区別をつける|を並べて最後に○を 3 個続けて並べれば,
○○|○|○○○
となって,「A が 2 個,B が 1 個,C が 3 個」という情報を伝える信号ができあがります。
同様に考えると,
A 4 個,B 2 個,C 0 個 → ○○○○|○○|
A 5 個,B 0 個,C 1 個 → ○○○○○||○
A 0 個,B 0 個,C 6 個 → ||○○○○○○
と表すことができます。そして,1 つの○と|の配列に対して,商品の組合せが必ず 1 つだけ対応します。
よって,商品の組合せの総数は,6 個の○と 2 個の|を 1 列に並べる方法の総数に等しく,
\[{}_8 \mathrm{C}_6={}_8 \mathrm{C}_2=\frac{8 \cdot 7}{\;2 \cdot 1\;}=28\]
と計算することができます。